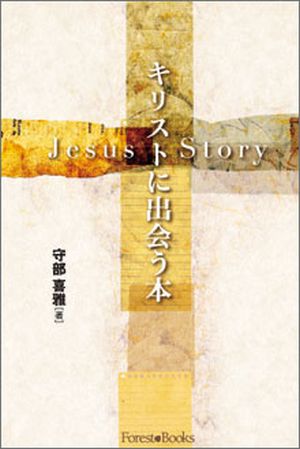日本人にとって、イエスとは誰なのか 漁師さんの本音
守部喜雅
クリスチャン新聞編集顧問
漁師さんの本音
日本人にとって、イエスとはどのような存在であるのか―この究極ともいえるテーマを考えるうえで、昨年、宮城県の牡鹿半島の被災した漁村で体験した出来事から話を始めてみたいと思います。
その夏の夜、漁師さんの頭ともいえる人の自宅で、被災した村の漁業をいかに再建するかが話し合われていました。被災して三年目を迎えていました。ようやく、ワカメや牡蠣の養殖が再開され、それをどう軌道に乗せるかが大きな問題となっていたのです。
*
話し合いは、午後九時まで続きましたが、それでお開きにはならず、そこから、「聖書タイム」が始まったのです。この漁村が被災して以来、ほぼ週の半分は、この村に通い続けた牧師が、ボランティア活動とともに、一年前から、強い信頼関係で結ばれた漁師の人々と一緒に聖書を読む会を始めていたのです。それが「聖書タイム」です。
筆者が参加したときには、ルカの福音書19章をみんなで輪読、まず、牧師が教えるのではなく、参加者全員に配られた新約聖書を手に、自分の感想を自由に語り合います。「どうして、ザアカイさんは木に登ったんだべ」といった質問も出てきます。どんな質問にも笑ったりしてはいけません。そのとき、初めて聖書を開いた漁師さんもいるからです。
ニコニコしてそのようすを見ている牧師も、上から目線で説教することはありません。すべての人が聖書から直接学ぼうという雰囲気は感動的でした。
*
会も半ばになった頃、頭が突然発言したのです。
「おれさ、イエス様が神様ちゅうことは分かるんだ。だけんど、イエス様がどうして、一番の神様かが分かんねえ」
これには驚きました。頭は、日本人の精神性をみごとに代弁していたのです。日本には、偉人が神になるという精神風土があります。明治天皇に殉死した乃木将軍は、その死後、神として祀られて乃木神社ができ、徳川家康を祀るためにできた日光東照宮が、今も人々が拝む聖域になっています。漁師の頭にとっても、イエスをそのような偉人の一人として、神として崇めることに抵抗がないのです。
面白いことに、その漁師さんの自宅には、当然、海の神を祀った神棚があるのですが、牧師からイエス様のことを教えられて以後、その神棚の横に新約聖書がお供え物のように置かれていました。頭は、イエス様がすばらしい方とは認めても、その方が、唯一の神であり、唯一の救い主ということが分からないのです。
しかし、少しだけですが希望はありました。その「聖書タイム」が終わる頃、頭が、しみじみと言った言葉が忘れられません。 「おれさあ、イエス様のこと、もっと知りてえんだ」
日本人は寛容か?
「日本では誰でもその想像に委せて、神様を造ることが自由にできる。宗教上、信者相互の寛容が非常に大きいのもこうした結果であって、一神社内に、往々異なった色々の神が、互いに隣り合って祀られてあったりする。従って私は、もし日本人が、歴史上キリスト教徒のことについて、何も知らないならば、彼等は平気で日本の神様の傍にキリストの像を祀ったであろうと信ずる。私は或る時、一人の日本人が、彼は喜んでキリストの有難さを信ずるが、しかし、だからといって、キリスト教徒の優越を信ずることはできないと語ったのを聞いたことがある」(『長崎海軍伝習所の日々』平凡社、一六一頁)。これは、一八五七年、長崎海軍伝習所の教官として来日したオランダの海軍武官カッテンディーケが、その回想録に残していることばです。彼は、勝海舟に信仰的影響を与えた人物で、作家の司馬遼太郎は、カッテンディーケが勝に与えた影響は、坂本龍馬の人生にも受け継がれているとさえ語っています。
彼は、日本に来て、日本人の寛容さに驚きます。しかし、それは、日本には相対的世界観しかなく、それは絶対的真理を求めることを困難にしている精神風土であることも見抜いていたのです。ここに、牡鹿半島の漁師さんが、いみじくも言った、「イエス様が一番の神様かが分かんねえ」ということばに符号するといえましょう。
イエスとの出会い
ここで、筆者自身がどのようにしてイエスと出会ったかについて述べてみます。十九歳のとき、音楽会と間違えて教会の集会に迷い込んだわたしは、そこで、初めて、イエスのことばに出会います。
「わたしが、道であり、真理であり、いのちなのです」
伝道集会の会場に掲げられた横幕に書かれていたこのことばは、初めての者にはかなり刺激的でした。こんな大げさなことばを言えるのは二種類の人間だけだとも思いました。一種類めは世界一のペテン師、もう一人は、もし神が存在するなら、神のような人物なら、こんなことばも許される。
イエスはいったい何者なのか。当時、宗教に関心のなかった私ですが、さすがに、イエスを世界一のペテン師とは思いませんでした。では、イエスは神なのか、それも分からないままに、しかし、このことばの権威に圧倒されたわたしは、イエスを求める旅に出たのです。そして、わたしとイエスを結びつけるキーワードを発見したとき、わたしの信仰者としての歩みが始まりました。キーワードとは何か。それは「わたしは神の前に罪人である」ということです。
言い換えるなら、「自分は救われなければならない罪人である」と分かったとき、イエスを救い主として、わたしの人生の主として受け入れ、このお方に従っていく道を選び取ったのです。イエスとは、人間の歴史上現れたたぐいまれな偉人としてではなく、このお方以外に救いうる名は誰にも与えられていない、そのような唯一の神、救い主として信じ、愛するとき初めて、わたしたちが“キリストに出会う”ということが実現するのではないでしょうか。拙著『キリストに出会う本』(フォレストブックス刊)は、そのような問題意識からまとめた小冊子です。
『キリスト伝』の魅力
最近、五十五年前に読んだ『キリスト伝』を再読して驚いたことがあります。この本は、イギリスの牧師ジェームズ・ストーカーが十九世紀末に書いた『キリスト伝』(村岡崇光訳・いのちのことば社刊)です。何に驚いたかというと、当時は、信徒向けのキリスト伝と理解していたのですが、今回、村岡崇光氏の改訂訳を読んで、これは、教会内で読まれるだけでなく、魅力あるキリスト教文学として、一般の人々にもぜひ読んでほしい一冊だということです。
もちろん、キリスト伝ですから、新約聖書に沿って物語は描かれています。しかし、この本の魅力は、現代人にも通ずる人間が持つ悲しみや罪を追究しつつ、人間イエスが十字架に死んだのは、まさにその人間の罪ゆえだったことをみごとな物語として提供していることです。文学としての力は、キリスト教に無関心な人々にも大きなインパクトを与えるに違いありません。
本文の中で、引用したい箇所は無数にありますが、ここでは、最後の結語の一部分を紹介して終わりたいと思います。
「歴史におけるキリストの生涯は、終わることがない。彼の感化はいよいよ増し、まだキリストを知らない死せる民はそれが届くのを待っている。それは新しい世界の建設に熱心に励んでいる人々の希望である。近代世界のいっさいの発見、人類のより正しい理念、より高い力、より繊細な感情の発達は、いずれも彼を解釈するための新しい手立てにすぎない。また、日々の生活を彼の理想と彼の人格の水準にまで高めることこそ、人類に与えられた課題である」(二一四頁)。