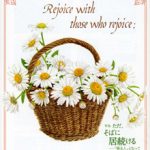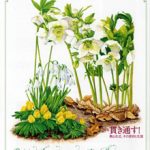特集 星野作品の原点―心の軌跡をたどる 神様が取っておいてくださった企画
編集ライター 熊田和子 星野富弘さんの四年ぶりの詩画集『あの時から空がかわった』ができました。今回の作品集は「蔵出しのお宝と新作および人気作品」のみごとなコラボレーションです。そこに、詩画に寄せた書き下ろし […]
特集 星野作品の原点―心の軌跡をたどる 神様が取っておいてくださった企画 私の感じる星野作品の魅力
富弘美術館 学芸員 桑原みさ子 「不思議だね、来た時には何とも思わなかった花が、帰りはすごくきれいに見えるね」 先日、富弘美術館に来館された中年ご夫婦の会話です。美術館の出入り口に生けてある白花の侘助(椿の […]
特集 聖書から見える父親像 まことの父への旅路
日本福音キリスト教会連合 門戸聖書教会 牧師 徳永 大 私の脳裏に焼きついている最も幼い日の記憶は、母に抱かれて夜汽車の窓に映っている自分の姿です。私が三つの頃、母は私を連れて、逃げるように家を出ました。父の女性問題が原 […]
特集 聖書から見える父親像 父となること
日本福音自由教会協議会・鳩ヶ谷福音自由教会 大嶋 重徳 著者がどれほど内面と向き合い、時にえぐり出し、人生を遡り、これらの言葉が綴られたのだろうか。読みながら、この問いが繰り返し起こってくる。そして自分を代表する「父とな […]
【特集】日常語訳で神の言葉を読む 『リビングバイブル』全面改訂①
『リビングバイブル』が今春ついに全面改訂。聖書を「いつかは読みたい」と思っている方や、読み始めても続かない方、必見! 聖書に親しみ、福音に触れる グレース宣教会 学園前グレースチャペル 牧師 大久保八城 & […]
【特集】日常語訳で神の言葉を読む 『リビングバイブル』全面改訂②
一般的な言葉で聖書を説明できる TEAM宣教師 ドン・E・リギア 伝道に従事する私たちは、これまでに一度も聖書を読んだことのない日本の人々と出会います。 教会でよく用いられている聖書を、まだ聖書をまったく読んだことのない […]
ただ、そばに居続ける─「隣る人」となって 人が人を慈しむ「手触り」の映画として
稲塚由美子『隣る人』企画 映画を観たある人はこう呟いた。「自分が小さい頃の、抱きしめられなかった寂しい気持ちが呼び起された」「私の『隣る人』は誰だろう。私は誰かの『隣る人』になれるのだろうか」「舞台となった〈光の子どもの […]
ただ、そばに居続ける─「隣る人」となって 生まれて初めて味わう家族の愛
柏木道子大阪キリスト教短期大学 元学長 近年、新聞で児童虐待の記事が頻繁に報道され、心がひどくかきむしられる思いを感じていた。それらが氷山の一角であること、しかも虐待をするのは実の母親および関係のある父親がほとんどである […]
死といのちを見つめて 混沌とした難しい時代にホスピス
細井 順ヴォーリズ記念病院 ホスピス長 大規模災害、原発再稼働の流れ、安保関連法案可決、多死社会の到来など、生死を語らざるをえない時代が来ている。わが師匠、柏木哲夫先生は「ホスピスケアとはその人がその人らしく尊厳をもって […]
死といのちを見つめて 死と向き合って今を生きる
死は、日本では忌み嫌われてきました。日常「死」を話題にすることは、はばかられるのが常でした。しかし、そんな中でも、しばらく前から「デスエデュケーション」という言葉が知られるようになってきました。生と死について学び、尊厳あ […]
貫き通す!
―高山右近、その信仰と生涯 月刊マンガ「らみい」に連載された高山右近の生涯を描いた『キリシタン大名 高山右近』が出版された。
信仰面もしっかりと描かれた、その作品の魅力に迫る!
坂下章太郎さいたま福音キリスト教会/東京メトロポリタンチャペル 牧師 「全世界に出て行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えよ」(口語訳聖書マルコによる福音書十六章十五節。フランシスコ・ザビエル宣教師が愛した主の大宣 […]
貫き通す!
―高山右近、その信仰と生涯 漫画家・青山むぎさんインタビュー!
◆なぜ、「高山右近」を題材に漫画を描こうと決心されたのでしょうか。 子どもたちの心が神様に向くようなもの、信仰の手本となるようなものを描けたらと考えていたときに右近を知りました。教会の二十周年記念会で、中村敏先生が日本キ […]
みことばに「聴く」―牧師室の霊想から
礼拝のために大切な説教を備えてくださる牧師の日々のディボーション、聖書の読み方をのぞき見! 少しずつ増えていった私の聖書読み
鈴木崇巨日本基督教団 上総大原教会 説教者 私は高校生になってから教会に通うようになりました。私を導いてくださったのは、日本語の上手な宣教師でした。主に紙芝居や外国製の聖画を使って「放蕩息子」の物語や「良い地に落ちた良い […]